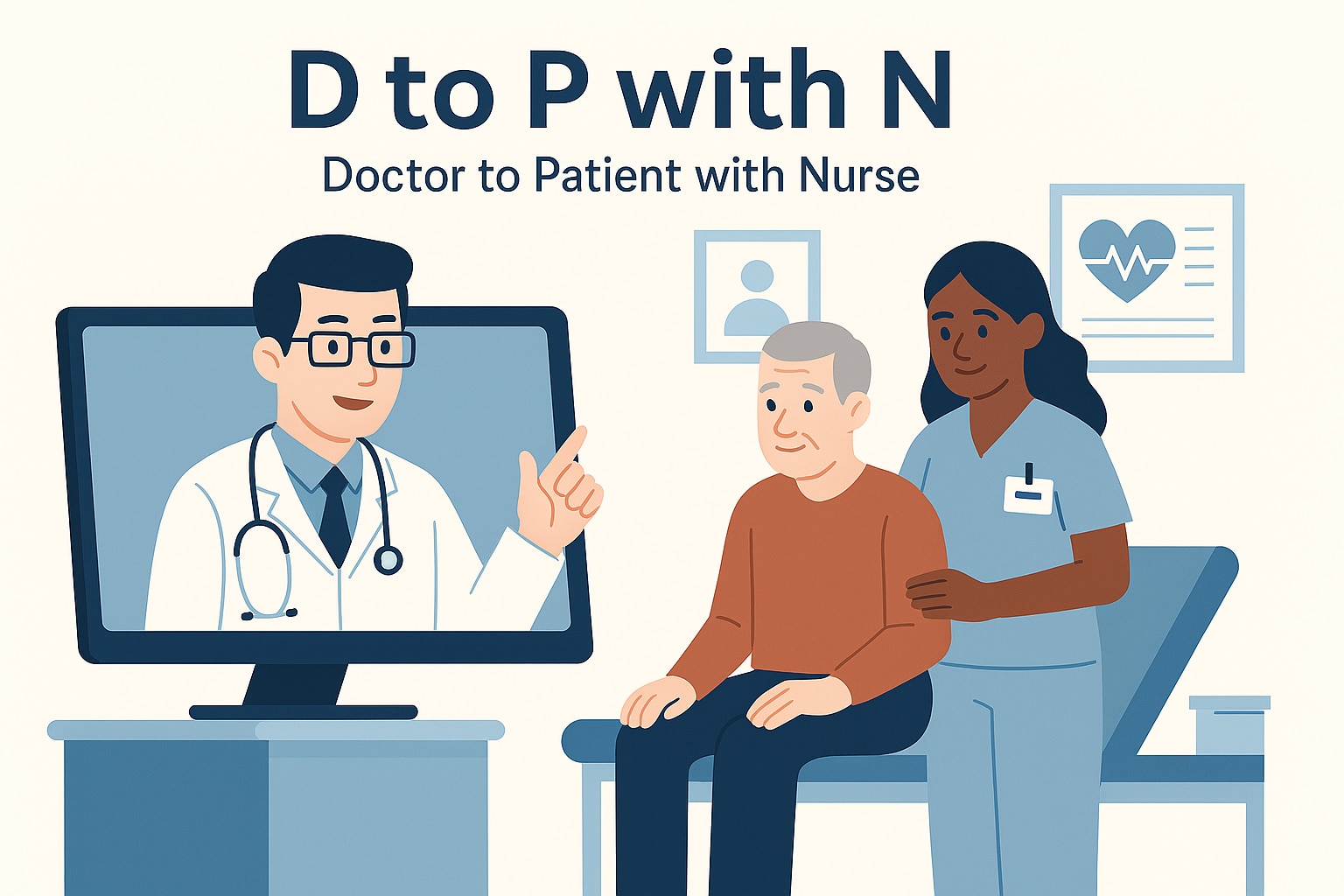
今注目されるオンライン診療 with Nとは?
※この記事はAIによる自動生成を含みます。誤りや不正確な情報が含まれる可能性がありますので、参考情報としてご利用ください。
近年、医療現場では「在宅医療」のニーズが高まる中、新たな診療形態として注目されているのが「オンライン診療 with N(D to P with N)」です。
特に高齢者や通院困難な患者に対して、医師の移動負担を軽減しつつ、質の高い診療を提供できるこの仕組みは、今後の在宅医療のスタンダードとなる可能性を秘めています。
本記事では在宅医療でのオンライン診療 with Nについて簡潔にご紹介します。
目次[非表示]
オンライン診療 with N ( D to P with N )とは?
「D to P with N」とは、「Doctor to Patient with Nurse」の略で、医師が遠隔からオンラインで診療を行い、患者のそばには看護師が同席して診療を補助する形態です。従来のオンライン診療(D to P)では、患者が自ら端末を操作する必要があり、高齢者や要介護度の高い患者にとってはハードルが高いものでした。
しかし、D to P with Nでは、看護師が機器操作やバイタル測定、必要な処置をサポートすることで、患者は安心して診療を受けることができます。医師も、看護師の補助により、より正確な診断や治療が可能となります 。
▼ D to P with N の考え方
- 患者の同意の下、オンライン診療時に、患者は看護師等が側にいる状態で診療を受け、医師は診療の補助行為を看護師等に指示することで、予測された範囲内における治療行為や予測されていない新たな症状等に対する検査が看護師等を介して可能となるもの。
- D to P with Nにおいても、指針に定められた「最低限遵守するべき事項」等に則った診療を行うこと。
▼ D to P with N で実施可能な診療・診療の補助行為
- 医師の指示による診療の補助行為の内容としては、「 診療計画 」 及び訪問看護指示書に基づき、予測された範囲内において診療の補助 行為を行うこと。
- オンライン診療を行った際に、予測されていない新たな症状等が生じた場合において、医師が看護師等に対し、診断の補助となり得る追加的な検査を指示することは可能である。
▼ D to P with N の提供体制
- D to P with Nを行う医師は、原則、訪問診療等を定期的に行っている医師であり、看護師等は同一医療機関の看護師等あるいは訪問看護の指示を受けた看護師等である。
出典:厚生労働省『オンライン診療の適切な実施に関する指針』
自治体等によるオンライン診療 with Nの取り組み
厚生労働省は、オンライン診療の適切な実施に関する指針を見直し、D to P with Nを正式に診療形態として位置づけました。これにより、自治体や医療機関は制度的な裏付けを得て、導入を進めやすくなっています 。例えば、離島や山間部など医師の常駐が難しい地域では、看護師が常駐し、基幹病院の医師とオンラインで連携することで、日常診療をカバーする事例が報告されています 。
■ 国立病院機構岩国医療センターの事例
離島における診療機会の増加や悪天候により医師が訪問できない場合にオンライン診療を適用することで、医療機関側と患者側双方で効果を得られたことが報告されています。
▼ 医療機関側の導入効果
- へき地における診療機会を維持することで患者に定期的に診療を提供できる
▼ 患者側の導入効果
- 医師と対話できる診療機会が増え、満足感を得られる
- 悪天候でも診療機会を確保することができ、医療機関と繋がっている安心感が得られる
■ 僻地医療についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
出典:厚生労働省『 オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集』
在宅医療でオンライン診療が求められる理由
在宅医療の現場では、患者の通院負担や医療従事者の移動負担が大きな課題です。特に高齢者や慢性疾患を抱える患者にとって、定期的な診察は不可欠ですが、訪問診療や往診には限界があります。
オンライン診療 with Nは、こうした課題を解決する手段として有効です。
看護師が患者宅を訪問し、医師とオンラインでつなぐことで、診療の質を保ちつつ、移動の負担を軽減できます。また、感染症リスクの低減や医療資源の効率的な活用にもつながります。

訪問診療や往診を代替するオンライン診療 with Nの事例
実際に、訪問診療や往診の代替としてオンライン診療 with Nが活用されている事例も増えています。例えば、慢性疾患を抱える高齢者が定期的に訪問看護を受けているケースでは、診療計画に基づき、看護師が医師の指示を受けて必要な処置を行うことで、医師の訪問頻度を減らしつつ、診療の質を維持しています 。
また、予測外の症状が出た場合でも、看護師がその場で医師に報告し、追加検査の指示を受けることで、早期対応が可能となります。これにより、患者の安心感と医療の安全性が両立されるのです。
■ オンライン診療 with N の活用事例はこちらのウェビナーでもご紹介しています。
まとめ(オンライン診療 with N は在宅医療の未来を支える)
本記事では、「在宅医療」「訪問診療」「往診」の現場で注目されるオンライン診療 with Nについて解説しました。
- D to P with Nは、医師・看護師・患者の三者連携による新しい診療形態
- 自治体や厚生労働省も制度整備を進めており、導入が加速
- 在宅医療における迅速な対応と診療の質向上に貢献
- 訪問診療や往診の代替として、医師の負担軽減と患者の安心を両立
今後、医療機関がオンライン診療 with Nを導入することで、地域医療の質と効率が大きく向上することが期待されます。まずは、自院の診療体制や訪問看護との連携状況を見直し、導入に向けた準備を始めてみてはいかがでしょうか。
■オンライン診療 with Nの診療形態は、医師と看護師の事前連携が前提となっており、情報共有体制の整備が重要です。
kaleido TOUCHは、チャットでのコミュニケーションとオンライン診療をシームレスに行う仕組みをご提供します。
■ 在宅のオンライン診療 with N アプリ kaleido TOUCHのサービス紹介資料はこちら



